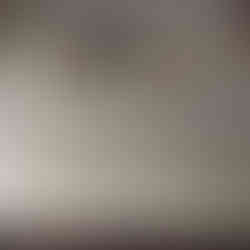*舞台
- 館主
- 2024年6月22日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年6月26日
記者:橋本光弘

舞台について書こうと思います。
■舞台に立つには環境が必要
自分のものづくりのきっかけはWindows用3Dゲームのハインド98というゲームだった。英語でどう遊ぶかわからなかったけれど本当に感動した。
3Dゲームを作りたくて書籍を探したが田舎の本屋には1冊しかなく翻訳はめちゃくちゃだった。さらにモデリングソフトは100万円を超えていた。
ゲーム制作どころか、まず3Dフォーマットを設計できなければ3Dモーションを動かすことすらできなかった。いつしかゲームではなく3D全般やネットワーク全般を学ぶことが目的になっていた。
同じ時期、米軍基地に行くことがあったが小学生が自由自在に3Dゲームを作っていた。無料のモデリングソフト、豊富なリファレンス、最初から用意されているライブラリ群、発表するためのプラットフォーム…環境が揃っているので何年も翻訳や車輪の再開発をせずアイディアとセンスに集中していた。
熱意やアイディアがあっても、環境がなければ舞台を目指すことは無謀だった。
■思っていた舞台とは違うけれど
時は経ち、ブロードバンドは普及しMMORPGが流行ったころ引きこもりになっていた。
両親のある種の寛容さにより研究に没頭していた。おかげでネットワーク技術と3D技術は個人で到達できる限界に達していた。プログラミング言語も整備され、ネットワーク環境もライブラリ環境も揃いつつあり念願のゲーム制作に着手することにした。しかし、今度は環境が揃ったがアイディアやセンスを磨いてこなかった事が足かせになった。
技術的に見せたい事は実現できるのにいくら考えてもストーリーやゲーム性が思いつかない。同世代は就職する時期だったのも相まって焦りだけが増えていく。今からアイディアやセンスを磨くなんて…その焦りで少しずつ追い込まれていった。
このやるせない感情を吐露できるオンライン空間、まだ珍しかった自由に動かせる3D空間、個人でも3DMMORPG作れる事を証明して世間を驚かせてから引退することにした。
後ろ向きの熱意は無謀ともいえる3DMMORPGをつくるプロジェクトへと変わっていった。
何カ月も寝ずに作り続け、3Dモデリングや音源などを手伝ってもらううちに、掲示板で噂になりテストプレイヤーが集まるようになった。気づくと3DMMORPGのテストプレイの反響は予想を超えて広がり多くの人を驚かせる目的が達成されてしまった。
そこで、問題が起きた。
個人契約のネットワーク帯域がパンクしプロバイダから月30万する事業用に変えて欲しいと警告がきた。サーバーは常にドライヤー2台分の電気代を消費しガリガリと家計を圧迫していく。早く換金方法を考えないと破綻してしまう。
当時はクレジットカード決済は個人が使えなくクラウドファンディングもなくお金を銀行に振り込んでもらって数百件を毎月一件ずつ確認するしかなかった。
個人で3DMMORPG作れないのではない、維持できないから誰も作らなかったのだと理解した。
サーバーのコンセントを抜くことを選んだ。
データを失ったユーザーによって炎上したが、無料だったこともあり大きな騒動にはならなかった。
少し時間が経ってから、その技術について本を出さないかという依頼が来て本を出すことになった。その結果、WEB系プログラマに就職も決まり引きこもりを脱することができた。
本来の目指していた舞台ではなかったものの観てくれる人はいた。結果的には1人の創作意欲を掻き立てることができた。
納得して舞台を降りることができた。
■舞台を愛するから舞台を降りる勇気
今までゲーム制作の情報や経験は独学で学んできた自負がある。そのたびに考えた工夫や集中力には自信がある。
同時に、インターネット黎明期に非常にすぐれた人々が技術や経験を無償で分け与えてくれたおかげでショートカットできたと感じている。環境が揃っていない時代に次の世代に委ねて舞台を降りた人たちが確かにいた。
もし彼らが舞台に上がることにこだわり続けたら環境はいつまでも整うことがなく質の低い舞台が薄っすら広がる世界になっただろう。
果たしてそんな魅力の低い世界で舞台にあこがれる人は現れただろうか?
舞台とは、舞台に立つ人がすべてではない。向き不向きを受け入れて参加した先に舞台がある。
舞台で演じる人、舞台に上がる人に教える人、舞台を維持し整える裏方の人。降りた先でも舞台を熱く語り1人を魅了できたなら舞台のために生きたといえる。
■初心を忘れない教室を
環境を作り出すのは1人の人生を浪費しても全然足りない。
先人たちも舞台に上がりたいと願いつつ環境構築に力尽き次に託すことが行われてきた。その祈りに近い想いを無駄にしないためにも環境の再生産できるような場所を作ろうと思っている。文化を作ろうともがいた先人たちへの敬意、初心を忘れない教室。
ものづくりへの感謝を、文化を支えようとする人への敬意を表す舞台。それが別館の教室。